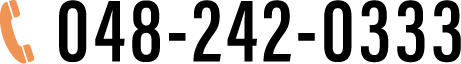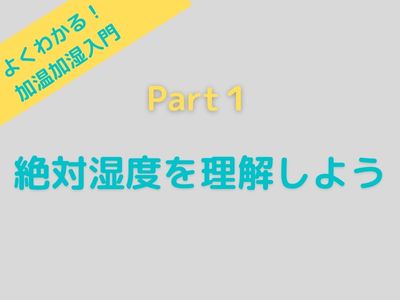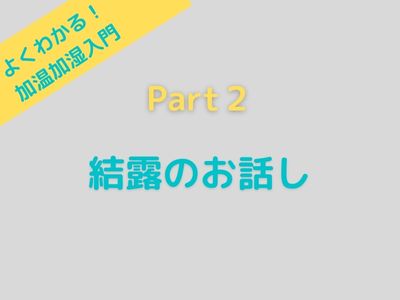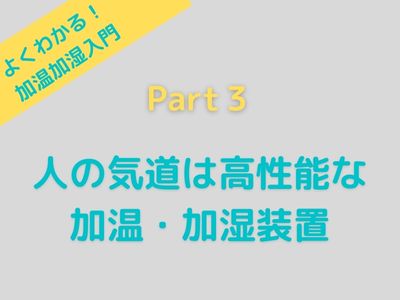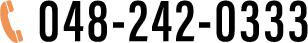【よくわかる!加温加湿器入門 part30】気管切開に人工鼻は必ず必要なの?と~ちょっと詳しく考えてみましょう~
前回は、気管切開で使用される人工鼻を装着中に酸素を投与する時の加湿について説明しました。
今回も、気管切開用の人工鼻について、臨床での経験を含めて説明していきます。
気管切開をして、酸素投与をしている小児の患者さんがいました。酸素は人工鼻にある酸素投与の接続部から投与されていましたが、SpO2は92%前後で不安定な状態なため、相談の連絡がありました。患者さんのところに行くと、気管切開口からの気管吸引をしていました。気管吸引を終了して、人工鼻を装着しましたが、SpO2は92%前後です。そして、数分後にゴボゴボと分泌物が噴出してきて、患者さんは苦しそうになりました。また、気管吸引です。詳しく聞いてみると、気管分泌物が多量で、気管吸引が頻回で、人工鼻も詰まるため、1日に5個ぐらい使用しているとのことでした。私が患者さんのところに行った時は、すでに人工鼻は分泌物で詰まっている状態で、酸素は1L/分を使用していました。この人工鼻、詰まっているから交換してみてとお願いし、人工鼻の交換をしましたが、数分後にこの人工鼻も分泌物がべったりと付着してしまったのです。この感じだと、人工鼻は1日に100個ぐらい必要になる。。。
1個500円なら、1日50,000円!
この患者さんのSpO2が低下するのは、分泌物で詰まった人工鼻を使用しているためであり、呼吸苦もこれが原因である考えました。そこで、気管吸引を行った後に、「人工鼻を装着しないで」とお願いしました。そうすると、酸素も投与されていないのに、SpO2は98%で安定しました。呼吸苦も減り、気管分泌物でゴボゴボと音を立てることも少なくなくなりました。気管吸引の回数は減ったものの、やはり気管分泌物は多いため、気管切開チューブから、分泌物が吹き上がってきます。この様な時にどうしたらよいのか。
「気管切開には人工鼻を必ず使用しなければいけない。」こう考える必要はありません。
この様な患者さんには、15㎝×15㎝程度のガーゼ3枚ぐらいを斜めに織り三角にし、その斜めの部分に紐を通して、ガーゼをクビに装着します。
このガーゼを気管切開口の上に被せます。このガーゼは、あくまでも気管切開口から埃などをブロックするためのもので、感染予防としてはあくまでも姑息的な対応です。ガーゼに呼気の水分を含んでくれれば、次の吸気で若干加湿された空気が吸えるようになりますが、この効果も決して多くはありません。気管切開口から分泌物が吹き出したら、このガーゼに付着するので、汚れたらガーゼの交換を行います。
気管切開口に人工鼻を装着することで、SpO2が低下することもあるのです。人工鼻が詰まってSpO2が低下するからと、酸素を投与するというのは、適正な治療方法ではありません。気管分泌物が多く、人工鼻がすぐに詰まってしまうのであれば、あえて、人工鼻は使用しないことを選択しましょう。
人工鼻が詰まれば、息が正常にできません。呼吸が苦しくなれば、低酸素状態にもなり、高炭酸ガス血症にもなります。気管切開口を三角に織ったガーゼを被せる方法は昔から行われてきたことです。
人工鼻を使用するのが当たり前で、ガーゼを被せるなんて昔の方法をするなんておかしいよ!と考えることもあるでしょうが、発展した医療で適正と思われる方法を行うことが、患者さんを苦しめることもあります。 昔の方法も知っておくと、患者さんの状態に合わせて、今、何をしたら患者さんが一番、安楽な状態になるかを考えて、様々な応用ができるようになります。
さて、この患者さんですが、夜間になるとSpO2が低下するとのことで、夜間は酸素投与をしたいとの希望がありました。使用していた酸素投与ポートの付いた人工鼻から、人工鼻のフィルター(ろ紙)を取り外しました。ろ紙を取ったことで開放された部分には、包帯が3重になるように固定しました。これで、ろ紙のない空っぽの人工鼻で酸素投与が可能となりました。包帯が分泌物で詰まったら、包帯だけを交換すれば良いことになります。ろ紙の外した人工鼻をいくつか作っておけば、洗ったり消毒したりできます。こんな方法は正しい使い方ではない!と言われることもあるでしょう。しかし、この方法によって、患者さんの呼吸苦は減り、気管分泌物も減り、SpO2の低下も減ったという事実から、今、自分の職場にあるものを如何に使って、対処することも必要だと考えます。
今回は、気管切開に装着していた人工鼻が分泌物が詰まってしまい、SpO2が低下する患者さんの経験について説明しました。 気管切開には人工鼻を必ず装着する。。。 この考え方は患者さんにとって必ずしも適正ではありません。 臨床の現場では、様々なことが起こりますので、知識と経験を応用して、デバイスを使いこなしていくということが大切であると思います。
次回も、気管切開用の人工鼻について説明したいと思います。
~この記事の執筆者~

松井 晃
KIDS CE ADVISORY代表。臨床工学技士。
小児専門病院で40年間勤務し、出産から新生児医療、急性期治療、慢性期医療、在宅医療、ターミナル期すべての子供に関わり、子供達から“病院のお父さん”と呼ばれる臨床工学技士。
小児呼吸療法を中心としたセミナー講師や大学の講師などを務める。著書多数。