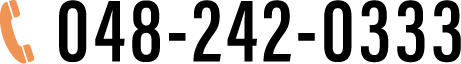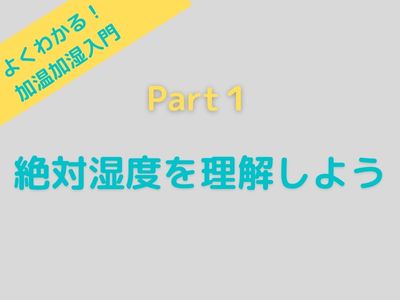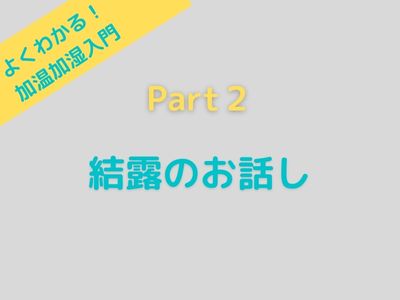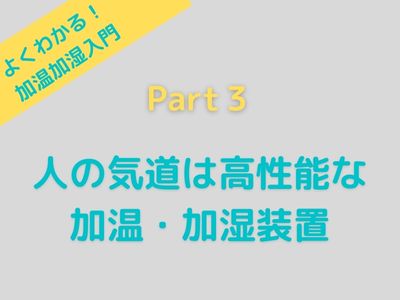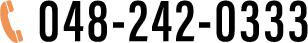【よくわかる!加温加湿器入門 part24】 加温加湿器の設定②低体温療法時はどうするの?
前回から、患者の病態に応じた人工呼吸管理における加温加湿器の設定についての説明になりました。前回は、「発熱疾患における設定について」でした。
今回は、低体温療法時の加温加湿器の設定について考えてみましょう。
低体温療法は、心停止を起こした後、CPR(心肺蘇生)によってROSC(Return Of Spontaneous Circulation:自己心拍再開)に至り、病院に搬送された場合に行う脳保護を目的とした治療法です。これは心臓が止まっているとき、脳血流は低下もしくは停止した状態となり、酸素不足に陥ります。ROSCできたとしても、脳の酸素不足によって後遺症が起こります。脳は3分間酸素が途絶えると脳は不可逆的な状態となり正常に戻らず、時に脳死状態になることもあります。
低体温療法は、体温管理療法(TTM: Targeted Temperature Management)」は いわゆる「低体温療法(Therapeutic Hypothermia)」と「平熱療法/常温療法(Antihyperthermia,Induced normothermia)」を含み、高体温を回避することで脳障害の進行を防ぐことに加え、中枢神経の保護作用を期待する治療法になります。 TTMの実施で二次性脳損傷を予防し、転帰改善に繋がると考えられており、PCAS(心停止後症候群)患者において、ROSC後に昏睡状態の患者ではTTMを行うことが推奨されています。 TTMは、32℃~36℃の範囲で目標体温を選び、その体温に達したら、少なくともその状態で24時間以上維持するTTMを施行するべきであるとされています。
体温の測定は体の深部体温であり中枢体温を反映する部位にて測定する必要があります。新生児蘇生では食道温によって体温を制御することになっています。 私の個人的な考えになりますが、食道は下降大動脈と平行して走っているため、心臓から送りだされた血流温を良く反映します。食道温は大動脈血流温であり、脳に送られている血流温とほぼ同等であると考えられます。
心臓外科の開心術において人工心肺装置が使用されますが、この時に低体温療法が併用されます。人工心肺装置から送血される血液の温度を低下させ、この血液を大動脈に送血することで体温を下げることができます。これは中心冷却法になりますが、この時の食道温は、送血温度を反映しています。 開心術における低体温療法は、送血する血液温度を下げる中心冷却法と体表面から冷やすことによる表面冷却法があります。
中心冷却法の方が、速やかな体温コントロールできるため、ECMOを使用した低体温療法を行う施設もありますが、一般的には体表面から冷却する表面冷却法が行われます。 人工呼吸器が装着された患者さんの低体温療法が行われる場合、表面冷却法で体温制御が行われるのですが、人工呼吸器からの吸気ガスの温度は影響しないのでしょうか?
人工呼吸器からの吸気ガスの温度は、低体温療法に影響します。 特に小さな赤ちゃんでは影響を受け易いと考えていますが、成人でも体温に影響する可能性があることを考えながら治療にあたる必要があると頭の片隅に置いて頂けると良いと思います。 低体温療法とは異なることですが、加温加湿器の電源が切れてしまうと、新生児では容易に体温が低下します。 また、加温加湿器の温度を高くする設定にすると、発熱を起こし、発汗が起こり、汗疹ができてしまったという経験もあります。 体温コントロールにおいては、加温加湿器の温度はとても影響すると言っても良いでしょう。
人工呼吸器から送気されたガスは、主気管支を通過し気管分岐部に達し、両肺野に流れていきますが、気管は大動脈や脳に血液が流れる頸動脈などの傍を通過します。 したがって、人工呼吸器の吸気ガス温によって、脳に流れる動脈血を温めてしまうため、脳温を上昇させてしまうことを考えなければなりません。 新生児における低体温療法において、フィッシャー&パイケル社のMR850加温加湿器を使用する場合には、マスクモードにしましょうと言われています。 しかしながら、「分泌物が硬くなって引けなくなってしまう」時に、「気管チューブが詰まってしまった」ということが良く聞かれ、どうしたらよいかと質問を受けることも多いです。
線毛は何℃以下になったら止まってしまうのであろうと、よく考えるのですが、体温が低下すれば線毛の動きが低下することは容易に考えられ、時に線毛が停止することもあるのではと考えます。 MR850加温加湿器のAUTOモードのマスクモードでは、基本的に、加温加湿チャンバーの出口温を31℃になるように水温を制御します。 吸気温度が31℃ということは、絶対湿度は32㎎/Lになります。 体温が37℃であれば、絶対湿度が32㎎/Lであっても、気管分岐部から肺胞に流れる間に加温加湿され、肺胞では44㎎/Lの絶対湿度になります。 しかし、低体温療法中では、この加温加湿が気道で行われにくくなります。 肺胞に達する絶対湿度が44㎎/L以下であることによって、線毛運動は低下し、分泌物が硬くなり、人の持つ分泌物を排泄するという従来の感染防御システムが機能しなり、無気肺ができ、ガス交換にも影響する可能性があります。
また、低体温療法を開始してから、どのタイミングでマスクモードにすれば良いのか、体温を戻す時に表面加温をするわけですが、どのタイミングで挿管モードにすれば良いのかを考えなければいけません。 特に復温中に、急激に脳温を上げると痙攣などを起こしてしまうために、吸気温度の調整はとても重要になります。 低体温療法における加温加湿器の設定はとてもシビアに考えなくてはならず、その答えも患者ごとに変わってくるのではと思います。
筆者が埼玉県立小児医療センターで働いていた時、新生児の重症仮死の赤ちゃんに対する低体温療法を他施設よりも早い段階で導入しました。 そして、この時に加温加湿器の温度を何℃にすればよいのか相談されました。 この当時の加温加湿器はフィッシャー&パイケル社のMR730でしたが、口元温度を37℃、加温加湿チャンバー出口温を35℃という提案をしました。 この温度であれば、患者に送気されるガス温度は34℃程度になり、低体温療法の冷却時や復温時に影響しにくいのでは?と考えたのです。 この設定による低体温療法では、分泌物は硬くなるものの、引けないというレベルまでにはならなかったことや、気管チューブが詰まるということは一度も起こりませんでした また、復温時の合併症である痙攣を起こすこともありませんでした。 ということで、低体温療法には、口元温度と加温加湿チャンバー出口温度を任意に設定できる加温加湿器が必須であると考えます。
MR850においては、マスクモードで使用する場合はマニュアルモードのHC:3.0(口元温度:34℃、加温加湿チャンバー出口温度:34℃)に設定することを勧めていいます。 低体温療法における吸気ガスの温度は体温に影響するため、体温制御に影響しにくく、線毛運動を低下させず、分泌物を硬化させない温度に設定することが重要です。 この温度は、口元温度が37℃、加温加湿チャンバー出口温度が35℃程度が良いと筆者は考えており、患者の体温に併せて任意に設定できるMR730と同等の加温加湿器の使用が必要であり、Hydraltis(ハイドラルティス)9500FM加温加湿器は、この設定を行うことができます。
次回もお楽しみに。

~この記事の執筆者~

松井 晃
KIDS CE ADVISORY代表。臨床工学技士。
小児専門病院で40年間勤務し、出産から新生児医療、急性期治療、慢性期医療、在宅医療、ターミナル期すべての子供に関わり、子供達から“病院のお父さん”と呼ばれる臨床工学技士。
小児呼吸療法を中心としたセミナー講師や大学の講師などを務める。著書多数。